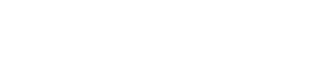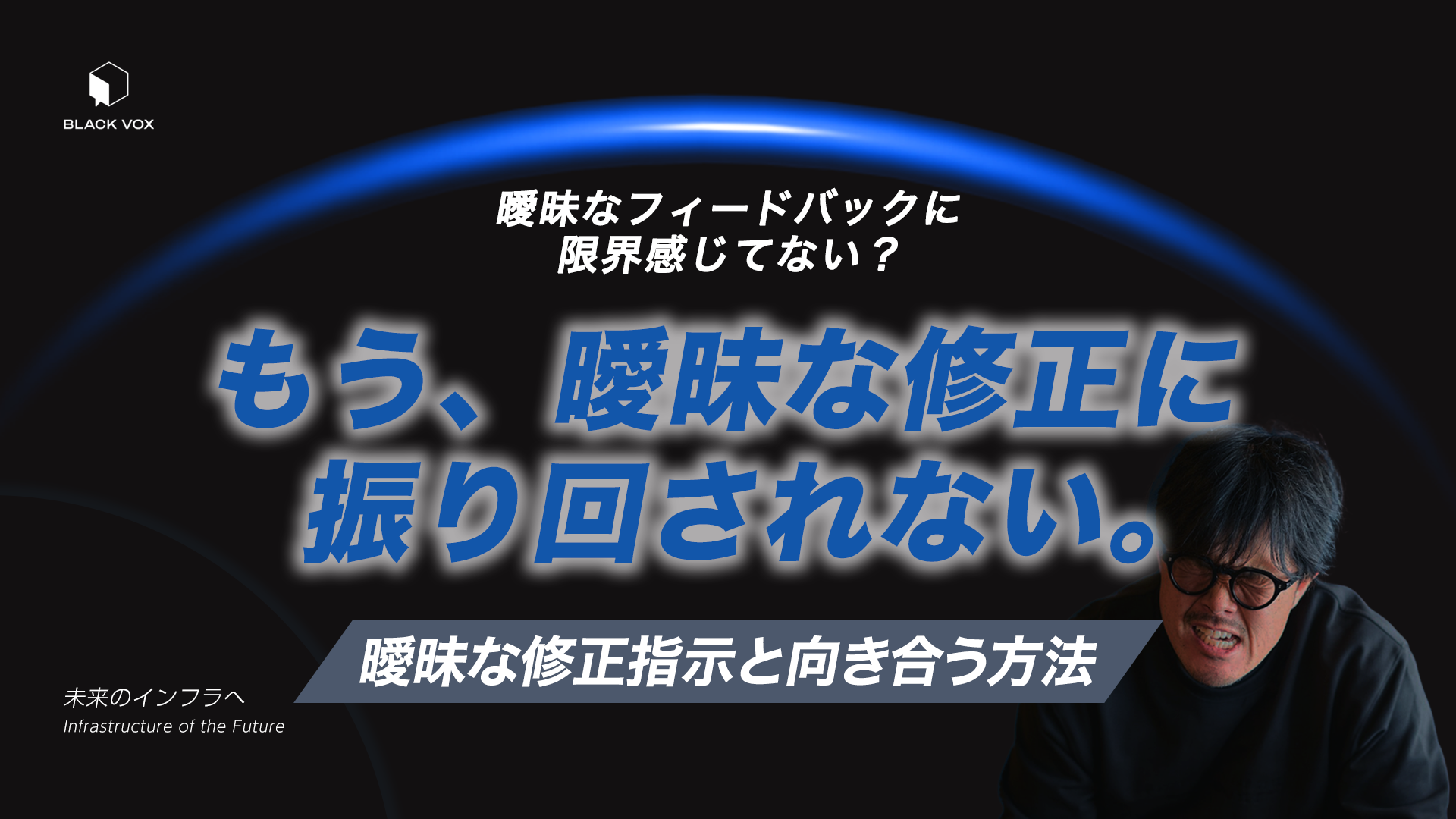“言った通りにやったのに…”の繰り返し
「もうちょっとやわらかく」、「なんか違うんだよね」、「もっといい感じで」そんな修正指示をもらったことありませんか?
あなたはその都度、全力で考えて、直して、提出してでもまた「違うんだよね」。
これはあなたのセンスや努力が足りないのではなく、言葉が曖昧すぎることが原因です。
この記事では、そんな伝わらない指示に苦しむすべてのクリエイターに向けて、曖昧な修正依頼との向き合い方、そしてストレスを減らすための具体的な方法をお届けします。
なぜ「なんか違う」と言われ続けるのか?
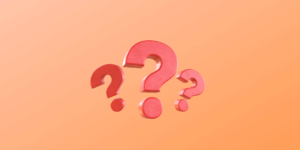
クライアントも「違和感の正体」を言葉にできていない
曖昧な修正指示を受けると、「ちゃんと伝えてほしい」と思いますよね。
でも実は、クライアント自身も「どこがどう違うのか」をはっきり言語化できていないケースが多いのです。
「なんか違う」と言われるたびにモヤモヤするのは、あなたの理解力の問題ではありません。
それは、感覚で抱いた違和感を言葉に変換するのが難しいから。
例えば…
- 「やわらかい雰囲気にしてほしい」→ 色味?フォント?演出?どれをどう変えるかは本人も明確でない
- 「もっとスタイリッシュに」→ 抽象的な印象語であり、具体的な修正点は提示されていない
このように、感情ベースのフィードバックは構造が曖昧になりやすく、受け取る側の解釈に委ねられてしまうのです。
つまり、問題は “悪気” ではなく “言語化の限界” 。
曖昧な修正指示がつらいのは、あなたのせいではなく“仕組み”の問題。
修正のやり取りがうまく進まないと、「自分の理解力が足りないのでは…」と感じてしまうこともあります。
でも、安心してください。あなたのせいではありません。
曖昧な修正指示が問題になるのは、情報の伝達に構造がないからです。
言葉だけでやり取りを重ねると、現場ではこんなことが起きがちです。
- 認識のズレからやり直しが発生し、手戻りが増える
- 修正内容の解釈が人によってズレて、修正が迷子になる
- 修正回数がかさみ、「ちゃんと伝えてるのに…」という不信感が生まれる
つまり、これは個人のスキルの問題ではなく、修正依頼のプロセスに “構造化されていない伝え方” が使われていることによる、システム的な問題なのです。
曖昧な指示と向き合うための3つの方法
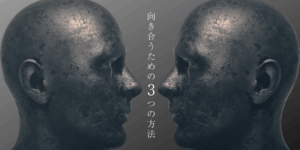
言葉の裏にある”意図”を掘り下げて聞く
クライアントにそのまま「もっといい感じって、たとえば?」と返すと、相手も困ってしまいます。
そこで有効なのが、なぜそう感じたのかの理由を聞くことです。
例:「どの部分が違うと感じましたか?」
→「フォントが固い感じがする」「ちょっと冷たい印象かも」
目的や印象がわかれば、自分で方向性を修正しやすくなります。
あえて「仮説」を提示して確認する
クライアントの曖昧な指示に対しては、受け身になるより「こういう意図ですか?」と仮説を返す方が伝わりやすくなります。
例:「“やわらかく”というのは、色味をパステルに寄せるという方向性でしょうか?」
仮説を立てることで、ズレを言語化できるきっかけを作れます。
言葉より「見せて」確認する
- 修正前と修正後の案を並べて提案
- 過去の実績や参考資料を一緒に提示
- 制作物に“直接”コメントをもらうツールを使う
文字情報だけでは伝わりづらい微妙なニュアンスも、視覚化されると一気に伝わりやすくなります。
曖昧な指示に振り回されないためのマインドセット
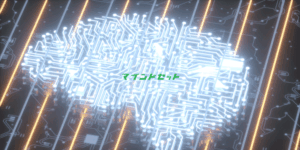
曖昧な修正指示は、あなたのスキルを否定しているわけではない
「なんか違う」「もう少し整えてほしい」「もっと良い感じで」そんな曖昧なフィードバックをもらうたびに、「自分のデザインがダメだったのか…」と落ち込んでしまうことはありませんか?
でも、ここで忘れてはいけないのは、その指示は決してあなたのスキルや努力を否定しているわけではないということです。
実は「もっと良くしたい」の気持ちの表れ
多くのクライアントが曖昧な表現を使ってしまうのは、「完成したものをさらに良くしたい」というポジティブな意図からです。
- 「やわらかく」という言葉の裏には、「視聴者に親しみを持ってほしい」という意図があるかもしれません
- 「もっと整えて」は、「ブランドの印象にもう少し近づけたい」という願いかもしれません
つまり、曖昧な言葉の裏には目的意識や改善の意欲があることも少なくないのです。
修正指示の意図を汲み取る視点が、制作の質を高める
曖昧な表現をただ否定的に受け取るのではなく、「この指示の背景には何があるのか?」という視点で考えることができれば、修正指示の本質が見えやすくなります。
それにより…
- 感情的なストレスが軽減される
- 主体的に提案できるようになり、信頼が高まる
- 結果として、制作物の完成度も上がっていく
「対話」こそが仕事の一部だと捉える
制作とは、“意図を形にする翻訳作業”です。
言葉になっていない部分まで汲み取るには、相手との対話が不可欠。
そのコミュニケーションもまた、あなたの仕事の価値です。
曖昧な指示の解消に役立つツール「BLACK VOX」
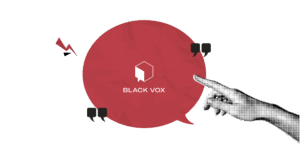
「ここです」と口で説明するより、「ここ」と画面上に指をさすように伝える方が早いし分かりやすい。
BLACK VOXは、そんな直感的なフィードバックを映像やデザイン制作物に“直接”書き込めるツールです。
**“メールで長文を書く”**でも”**どこを指しているか説明する”**でもなく、見たまま、思ったままにクリックしてコメントを残すだけ。
具体的には、次のようなことが可能です
- 映像やデザインにピンポイントでコメントを追加
- 時間や位置、要素ごとに「誰が・何を・いつ」伝えたかを自動で記録
- 修正ステータス(未対応/対応済み)も一覧で見える化
BLACK VOXを導入することで得られる3つの効果
1. 修正指示が明確になり、手戻りが激減
「どこの、なにを、どう直してほしいか」が、文章に頼らず可視化されることで、修正のズレや誤解が減ります。
2. メールやチャットに追われなくて済む
すべての指示やコメントが制作物上に集約されるため、メールを何往復もする必要がなくなります。
3. 「ちゃんと伝わったかな?」の不安が消える
相手の確認状況や、対応履歴が見えるので、コミュニケーションの不安やストレスが自然と減っていきます。
BLACK VOXは、“言葉で伝える”から“見て伝わる”に変えることで、曖昧な指示によるストレスを根本から解消するためのツールです。
「修正のやり取りに疲れてきたな…」と感じたら、ツールの力を借りるのもひとつの選択肢かもしれません。
「なんか違う」に疲れたら、方法と仕組みを見直そう
曖昧な修正指示にモヤモヤするのは、あなたが真剣に向き合っている証拠です。
でも、それで疲弊し続ける必要はありません。
- 意図を引き出す
- 仮説を立てて確認する
- ツールで視覚化する
この3つを実践すれば、曖昧なやりとりは“対話”へと変わり、結果として良い制作物につながります。
曖昧な修正指示にモヤモヤするのは、あなたが制作に本気で向き合っている証です。
でも、その熱量が伝達ミスや手戻りによって消耗してしまうのは、とてももったいないこと。
これからは「伝わらない」に悩み続けるのではなく、伝わる仕組みを取り入れていきましょう。
- 意図を引き出す質問をする
- 自分なりの仮説を立てて確認する
- 視覚的なツールで指示を共有する
この3つを意識するだけで、**曖昧なやりとりはすれ違いではなく「共創」に変わり、**結果として、クオリティの高い制作物が生まれやすくなります。
“もっと良くしたい” という思いを、ストレスではなく成果に変えるために
今こそ、やりとりの仕方を見直してみませんか?